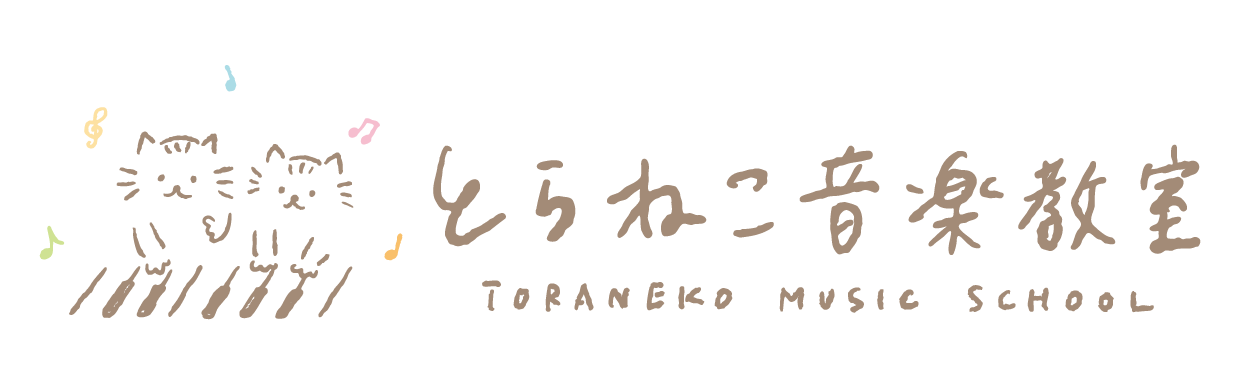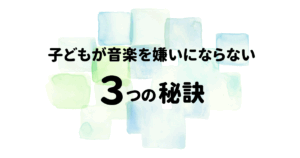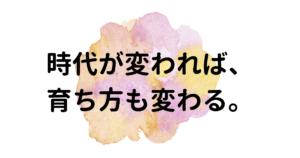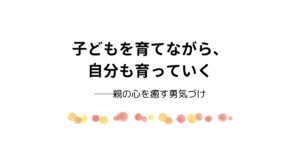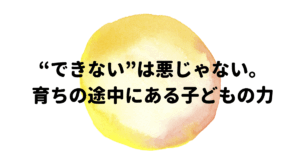「自己肯定感を育てたい」という言葉を、子育ての中でよく耳にします。
でも実は、アドラー心理学では、“それだけでは足りない”と考えます。
アドラーが大切にしたのは「貢献感」──
“自分は誰かの役に立っている”という感覚です。
自己肯定感は「ひとりで完結する安心感」
自己肯定感は、
「私は私で大丈夫」
「できても、できなくても自分には価値がある」
と、自分をそのまま認める感覚。
とても大切な心の土台ですが、
これだけだと、“自分の世界の中”で完結してしまうこともあります。
貢献感は「つながりの中で自分を実感する力」
アドラーは、人は「共同体の一員である」と感じたとき、もっとも健やかでいられると考えました。
そのために欠かせないのが、「貢献感」です。
「私は誰かの役に立っている」
「私がここにいていい理由がある」
この感覚があると、
人は自分を必要以上に大きく見せようとしたり、
失敗を極端に恐れたりすることが少なくなっていきます。
子どもにどうやって「貢献感」を育てる?
子どもが「役に立てた!」と感じる場面は、意外と身近にあります。
大切なのは、「うまくできたかどうか」ではなく、
「あなたがやってくれたことがうれしいよ」というメッセージを伝えることです。
たとえば──
- おもちゃを片づけてくれたとき:「手伝ってくれて助かったよ!」
- テーブルを拭いてくれたとき:「おかげで気持ちよくなったね」
- 自分から挨拶したとき:「挨拶してくれてうれしかったな」
子どもの行動が、“誰かの笑顔や安心につながった”と実感できるような声かけが、
貢献感を育む土壌になります。
家庭でできる「ありがとうの循環」
貢献感は、家庭という小さな社会の中でも、十分に育てていくことができます。
毎日の暮らしの中で、
親から子どもへ「ありがとう」
子どもから親へ「やってみたい」
そんなやりとりが自然に生まれる関係を目指していきたいですね。
ポイントは、“完璧でなくていい”ということ。
やろうとしていた姿や気持ちに目を向けることで、
子どもは「自分が誰かのためになれた」という手応えを積み重ねていきます。
おわりに:
「わたしには、ここにいる意味がある」
──その実感が、子どもを強くやさしくする
子どもが自分の力を信じ、他者とつながる力を育んでいくには、
「できるかどうか」ではなく、
「いてくれてうれしい」「あなたの存在に助けられている」
という声がけが欠かせません。
自己肯定感と、貢献感。
その両方があってこそ、子どもの心はしなやかに育っていきます。
✅次回予告(第5回)
親も自分を勇気づけながら育てよう ──インナーチャイルドとの向き合いと癒し