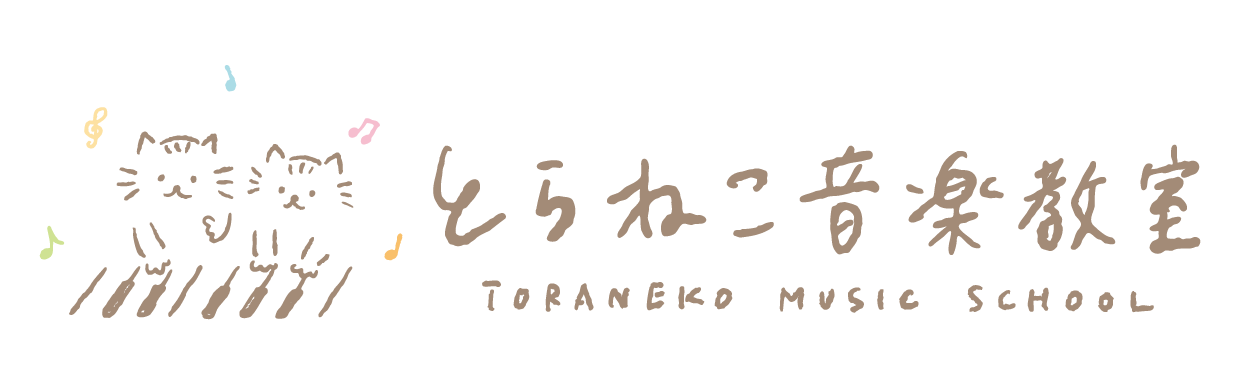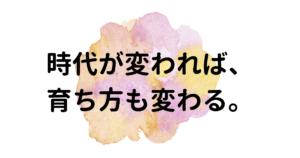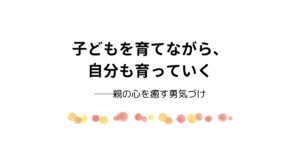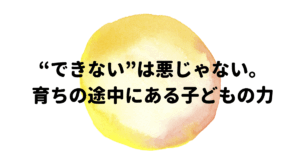「子どもには音楽を長く楽しんでほしい」――そう願うご家庭は多いのではないでしょうか。
しかし、無理をさせたり周りと比べたりすることで、せっかくの音楽が「苦手」「嫌い」「やりたくない」という気持ちに変わってしまうこともあります。
子どもが音楽を好きな気持ちを育むために大切なのは、上達のスピードや結果だけではなく、音楽そのものが持つ“楽しさ”を味わい続けられる環境です。
この記事では、子どもが音楽を嫌いにならず、好きでいられるために心がけたい3つのポイントをご紹介します。
1. 子どものペースを大切にする|比べないことが好きにつながる
気づかないうちに「ほかの子と比べる視点」や「年齢に応じた期待」が入り込むと、子どもにとっては大きなプレッシャーになってしまうことがあります。
けれども、成長のスピードは人それぞれ。音楽は競争ではなく、自分らしく表現するものです。
昨日より少し長く集中できた、去年より自然に歌声が大きくなった――そんな小さな変化を一緒に喜ぶことが、安心感と自信につながります。
その子自身のリズムで音楽と向き合えることが、心からの楽しさにつながっていきます。
2. 小さな成功体験を積み重ねる|「できた!」が意欲と楽しさを育てる
一曲丸ごと弾けなくても、1フレーズ歌えたこと、リズムに合わせて体を動かせたこと――これらも立派な「できた!」です。
こうした小さな成功体験の積み重ねが、「自分はできるんだ」という気持ちを生みます。
それが「もっとやってみたい」「次はこれに挑戦したい」という意欲へとつながり、音楽を続ける大きな力になります。
できた!という実感は、上達の証であると同時に“楽しさの芽”でもあります。
その芽を育てていくことが、音楽を嫌いにならないための土台になります。
3. 大人自身が音楽を楽しむ姿を見せる|最高のお手本は身近な人
子どもにとって、一番の手本は身近な大人です。
親が鼻歌を歌ったり、一緒に手拍子をしたり、先生が生き生きと演奏している姿――それは言葉以上に「音楽は楽しいんだよ」というメッセージになります。
逆に、音楽が「やらなくてはいけないこと」として伝わってしまうと、子どもにとっては少し窮屈に感じられることもあります。
大人が心から楽しむ姿を見せることが、子どもにとって音楽の本質的な喜びを伝える一番の方法です。
音楽は“間違えずにできること”よりも、“一緒に楽しむこと”にこそ価値がある。
そのことを、子どもは大人の姿から自然に学んでいきます。
まとめ|音楽の本質的な楽しさを伝えていくこと
子どもが音楽を嫌いにならないために大切なのは、
- 比べずに子どものペースを見守ること
- 小さな成功体験を積み重ねること
- 大人自身が楽しむ姿を見せること
そして、それらを通して伝わるのは、音楽は人を笑顔にし、心を動かすものだという本質的な楽しさです。
この楽しさを子どもがずっと感じられるように関わっていくことが、音楽を一生の宝物にしていく第一歩になります。