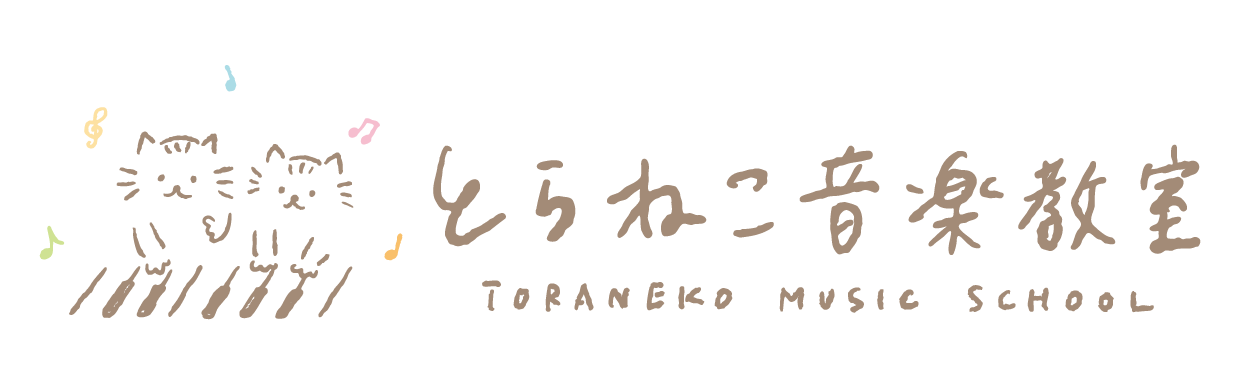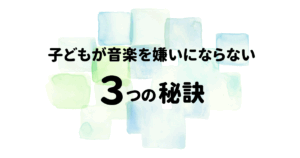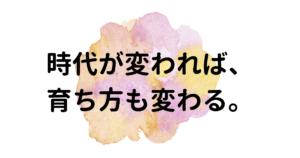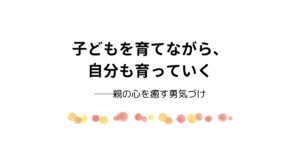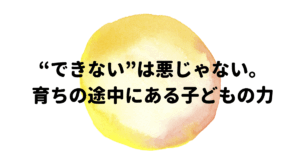「どうしてわざと困らせるようなことをするの?」
「こんなに何度も言っているのに……」
そんなふうに感じてしまう場面、子育ての中でありませんか?
でも実は、子どもの“困った行動”には、ちゃんとした理由があるかもしれません。
アドラー心理学では、こうした行動を「目的行動」と捉えます。
つまり、どんな行動にも“目的”があるという考え方です。
アドラー心理学の「目的論」って?
アドラーは、行動の原因を過去ではなく「目的」から見る心理学者でした。
たとえば、子どもが物を投げたとき──
「なぜそんなことを?」と“過去の原因”を探すのではなく、
「この子は何のためにそれをしたのだろう?」と考えます。
子どもの行動の奥には、たとえばこんな4つの目的があるとされます。
- 注目されたい(かまってほしい)
- 力を誇示したい(自分の意志を通したい)
- 仕返ししたい(傷ついた気持ちを伝えたい)
- 無力さを訴えたい(あきらめている)
「困った行動」は、“勇気がくじかれた”サインかも?
こうした行動は、単なるわがままや反抗ではありません。
子どもが「つながっていたい」「わかってほしい」と感じているからこそ、
その手段として、困った行動を選んでいることがあります。
特に、勇気がくじかれているときほど、表現が極端になる傾向があります。
たとえば──
- 注目されたい:騒いだり、やたらと話しかけてくる
- 力を誇示:指示に一切従わない、反抗的な態度
- 仕返し:モノを壊す、わざと冷たい言葉を言う
- 無力感:何を言っても「ムリ」「どうせダメ」
どう受けとめればいいの?
ここで大切なのは、「行動を正す前に、心に目を向ける」こと。
「この子はいま、どんな気持ちでこれをしているんだろう?」
「何を伝えたくて、この方法を選んだんだろう?」
こう問いかけることで、子どもの行動の奥にある“感情”や“ニーズ”が見えてきます。
声かけのヒント:感情に名前をつける
子どもが自分の気持ちをうまく言葉にできないとき、
大人が代わりに“名前をつけてあげる”ことはとても有効です。
たとえば──
- 「さみしかったのかな?」
- 「くやしかったんだよね」
- 「わかってほしかったんだね」
そうすることで、子ども自身も「自分の気持ちって、こういうことだったんだ」と気づき、
自分の感情を客観的に見られる力(メタ認知)が育っていきます。
おわりに:困った行動の奥にある“つながりたい”という気持ち
子どもが何か問題を起こしたとき、
「困らせようとしているんじゃないか」と感じてしまうこともあるかもしれません。
でも本当は、
「つながりたい」
「わかってほしい」
「大切にされたい」──
そんな、とてもまっすぐな気持ちのあらわれなのかもしれません。
行動だけでなく、その奥にある願いに目を向けていけたら、
親子の関係は少しずつ、あたたかく変わっていく気がします。
✅次回予告(第4回)
自己肯定感と「貢献感」ってどう違う? ──子どもの心に“わたしって意味がある”を育てる方法